
何が学べるの?
受験生のみなさんへ
こんにちは。大学へ進学し、世界史を学ぼうと考えている受験生のみなさん。これから、関西大学文学部総合人文学科世界史・地理学専修の世界史コース(2026年度入学生から適用。2025年度入学生までは世界史専修)で学べることを紹介していきます。進学の参考にしてみてください。関西大学の入試やオープンキャンパスの情報については「Kan-Dai web」をご覧ください。
何が学べるの?
日本の大学では、日本史、東洋(アジア)史、西洋(欧米)史などを学ぶことができますが、入学の時から特定のコースに所属、あるいは上位年次(2年次生以上)になってから日本史・東洋史・西洋史のコースに分かれることが多いです。すると、どうしてもその専門分野の歴史を中心に学んでいくことになります。それに対し、関西大学の世界史コースは、洋の東西の垣根をなくし、世界史全体を学ぶことができるカリキュラムをつくっています。私たちは6名の教員スタッフを擁し、世界各地の古代から現代にわたる歴史を学ぶことができます。世界史コースでの学びの最終的な目的は、高校までの歴史科目のように教科書の内容を時代順にたどって覚えることではなく、学生が自分でテーマを選び、史資料を収集・分析し、歴史を描くことにあります。教員は、学生のみなさんが自分に合った研究テーマを見つけて、学びが深められるようサポートします。
世界史コースの演習(専修ゼミ)で扱われるキーワードの例
- 東アジア古代・中世史、シルクロード史
- 東アジア近世・近代史、中央ユーラシア史
- 西アジア史(イスラーム化以後)
- 西洋古代史(古代ギリシア・ローマ史、古代オリエント史)
- 西洋中世史
- 西洋近世・近代史
- 西洋近現代史、戦後世界史
どのように学ぶの?
大学で歴史を学ぶのは、どこでも同じと考えていませんか? 実は、違います。上記のように、大学によっては入学する時から日本史、東洋史(アジア史)、西洋史などのコースに分かれてしまい、その分野を4年間、専門的に学んでいくところもあります。それに対し、関西大学が他大学と少し違うところは、1年生の間は専修に所属しないことです。入学時は文学部の総合人文学科に所属し、1年生の間に、歴史学やそれ以外の様々な学問をまなび、広く人文学の教養を身につけます。そして、2年生になる時、はじめて世界史・地理学専修に分属(分属希望時に世界史コースと地理学コースのいずれかを選択)しますが、ここでもアジア・欧米などの歴史、さらには人文学の諸分野を広く学びつつ、特定分野の歴史を深く学べるようになっています。学年ごとの詳しいカリキュラムは、下段の「1年次生へ」「2年次生へ」「3年次生へ」「4年次生へ」をご覧ください。
何が身につくの?

大学で世界史を学ぶことは、年号や用語の暗記を意味しません。世界史の中から明らかにしたい問題を設定し、事件や人物などの対象をしぼり、それに関する情報をできるかぎり集め、ジグソーパズルを完成させるように自分なりの歴史像を組み立てていきます。もちろん、パズルのなかには欠けているピースも多いのですが、そこは周辺のピース(集めた情報)から推測し、穴を埋めていきます。そして、自分の明らかにしたことが歴史の中でどのような意味を持つのか、解釈します。
さらに、考えたことを表現する力も養います。具体的には、研究の要点をまとめたレジュメ、あるいはパワーポイントのスライドを作って、ゼミで発表します。発表の後には、教員や他の学生との質疑応答を通してディスカッションを行います。考えた内容を文章化し、レポートとして作成することもあります。
世界史コースでは、こうした一連の学びを通じて、問題の発見、情報の収集と分析、プレゼンテーションや文章作成による表現、それにディスカッションといった、社会でも活用できるスキルと、長期的観点に立った広い視野を身につけることができるのです。
入学前に考えておくこと
ここからは、関西大学に合格し、進学を決めたみなさんへのメッセージです。世界史という外国の歴史を学んでいくためには、外国語の知識が欠かせません。もし、みなさんが、大学で学んでみたい歴史の国や地域を決めているのならば、第二外国語を選択する時、それに合わせてみましょう。フランス史ならばフランス語、ドイツ史ならばドイツ語、中国史ならば中国語といったように。もちろん、第二外国語にはない特殊な言語を使わなくてはならない国や地域もあります。それについては、入学後の文学部で独自に用意している授業がありますので、それを履修することができます。
もう一つは、大学4年間の学生生活中に、ぜひ短期でも、中期でもあるいは1年という長期でもいいので留学することを考えてみましょう。関西大学では交換留学や単位認定留学などの制度を用意しており、4年間で卒業できるような仕組みを作っています。
1年次生へ
入学おめでとうございます。ここでは、関西大学文学部で学生生活を始めるみなさんに、文学部での世界史の学び方と、1年次のあいだに履修することのできる世界史関連の授業を紹介していきます。2年次からの専修分属の参考にしてみてください。
1年次の学びについて
関西大学文学部は、1年次に人文学の様々な学問分野にふれて、2年次より専修に分属するという制度になっています。人文学のなかでも、歴史学はさまざまな学問分野と接点を持つ学際的な学問分野であり、幅広い学びがのちの研究に活きてきます。すでに世界史・地理学専修(世界史コース)に興味のあるみなさんは、1年次のうちに、世界史に関する授業を受けるだけでなく、他分野の授業や自主的な読書を通じて視野を広げることを心がけてください。同時に、世界でいま起こっていることに目を向けてほしいと思います。歴史学とは、すでに書かれた歴史を覚えることではなく、現在と過去との対話を通じて、歴史を書き換えていく営みだからです。
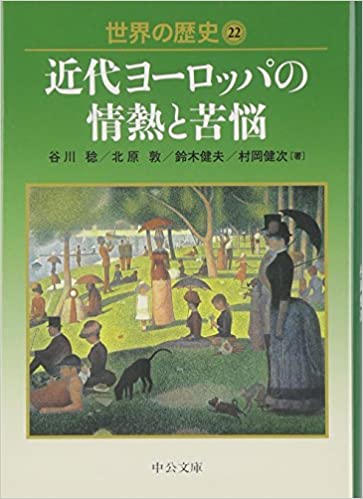
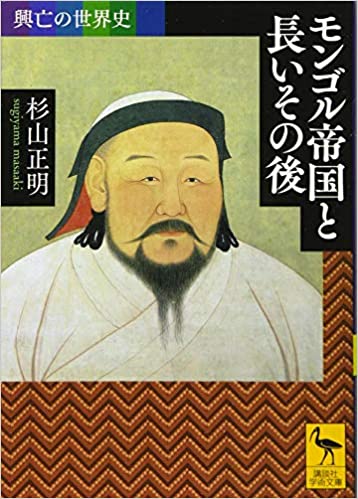
2年次から世界史・地理学専修(世界史コース)への分属を考えている場合は、世界史に関する入門書をできるだけ幅広く読んでみて、自分がどの時代・地域・対象に興味があるのか考えてみてください。例えば、『世界の歴史』(中公文庫)や『興亡の世界史』(講談社学術文庫)といったシリーズは、文庫本なので手軽に読むことができるでしょう。また、すでに興味のある分野があれば、それに関する新書や文庫本を読んでみましょう。
文学部では、例年12月に専修分属の希望を出してもらいますので、それまでに世界史・地理学専修や他専修の内容を把握し、どの専修を選択するかを考えてください。世界史・地理学専修に分属を希望する際は、世界史コースと地理学コースのいずれに分属するかの希望も出してもらいますので、各コースの内容も検討しておいてください。それに先立って、専修別の相談会(4月)や相談コーナー(11月)も設けていますので、専修選択に迷っている人や世界史専修についてより詳しく知りたい人は、相談に来てください。もちろん、世界史コースの教員に直接相談してもらっても構いません。
授業について
文学部では、1年次から世界史に関連する授業が多数開講されています。以下で紹介する個々の授業の内容については、シラバスで確認してください。
初年次導入科目
まず、初年次導入科目から紹介します。このうち、「学びの扉」は1科目が2単位で、2科目4単位が必修です。また、2年次に専修に進むためには、最低2単位は修得しておかねばなりません。世界史・地理学専修が提供している「学びの扉(世界史・地理学)」は、春学期と秋学期にそれぞれ一つずつ開講されていますが、両方履修することはできませんので、どちらか一方を履修して下さい。基本的にはどちらも同じ内容で、教員の専門分野に関する授業を行いながら、大学で学ぶ世界史と地理学の特徴・魅力を伝えます。
初年次導入科目「知へのパスポートa」(春学期開講)「知へのパスポートb」(秋学期開講)は、それぞれ1科目が1単位です。「知へのパスポートa」「知へのパスポートb」は専修ごとに提供されており、各専修の学びの内容を知るための入門ゼミの性格をもっています。これに対し、文学部で1年次生の時に必ず履修しなければならない科目「知のナヴィゲーター」(総合人文学科目、1科目1単位)では文学部共通の学びの基礎を学びます。ここに挙げた「知へのパスポートa」「知へのパスポートb」「知のナヴィゲーター」の3科目の中から2科目2単位が必修となります。また、2年次で専修に進むためには、これら3科目の中から最低1単位は修得しておかねばなりません。世界史・地理学専修が提供している春学期開講の「知へのパスポートa(世界史・地理学)」と、秋学期開講の「知へのパスポートb(世界史・地理学)」については、両方を履修してもかまいません。世界史・地理学専修では、いずれの学期も複数のクラスを開講していますので、各クラスの内容をシラバスで確認し、希望するクラスを登録してください。
その他の科目
次に、上にあげたもの以外に文学部の1年次生が履修できる科目で、世界史コースの学びに関連が深いものを紹介します。総合人文学科目では、「総合人文基礎講義(20世紀から現代社会を考える)」が、日本と世界の現代史に関わるテーマを扱っています。また、中学社会科ならびに高校地歴科の教員免許に関する資格関連科目としては、「東洋史概説a /b」や「西洋史概説a /b」などがあります。さらに、共通教養科目のなかにも「イスラーム世界の歴史を学ぶ」や「アジア文化交流史」「欧米世界の歴史と文化を知ろう」「西洋世界の社会と歴史を考える」「世界史の中の平和と戦争」「アジア史を学ぶ」「西洋の歴史を学ぶ」など世界史に関連する科目が多数ありますのでシラバスで開講時限と内容を確認し、関心があるものを履修してください。
また、世界史を探究する場合に、言語の知識は大いに役立ちます。文学部では、必修の外国語科目(第1選択外国語、第2選択外国語)以外に、文学部外国語科目として、英語、ドイツ語、フランス語、中国語の能力向上をめざす授業や、「西アジアの言語I/II(アラビア語、ペルシア語、トルコ語)」「古代エジプト語I/II」「ギリシャ語I/II」「ラテン語I/II」「サンスクリット語I/II」など多数の授業を開講していますので、みなさんの関心に応じて積極的に受講してください。
参考時間割(2026年度)
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
| 1 | 第2選択外国語Ⅱa/b | 知へのパスポート(世界史・地理学)a | 春学びの扉(世界史・地理学) 秋学びの扉(世界史・地理学) | 英語Ⅰa/b | 春知のナヴィゲーター | |
| 2 | 西洋史概説a/b | |||||
| 3 | 英語Ⅱa/b | 東洋史概説a/b | 第2選択外国語Ⅰa/b | |||
| 4 | 英語Ⅰa/b | |||||
| 5 | 知へのパスポート(世界史・地理学)a/b | 知へのパスポート(世界史・地理学)a/b |
注意点
①上の表は、1年次で履修可能な科目のうち、必修科目である外国語及び世界史・地理学専修(世界史コース)と特に関連の深い資格関連科目をあげたものです(共通教養科目などはここにあげていませんので注意してください)。時間割や履修のルールの都合上、1年次ですべてを履修することはできません。ハンドブックやシラバスを参照のうえ、希望に合わせて取捨選択してください。
②上の表にはあがっていませんが、教員免許や司書、学芸員などの各種資格を取得を希望する人は、「教育原理」「教職概説」など1年次生向けに開講されている資格関連科目を適宜選んで履修してください。
2年次生へ
晴れて世界史専修に所属することになったみなさん。これからの一年は、卒論に向けてどのゼミを選ぶかをじっくり考えて決めてください。2年次の秋学期半ば頃までには、卒論のテーマと3年次以降の所属ゼミについて、目処をつけておく必要があります。そのための判断材料となるのが、2年次に履修するゼミⅠ・Ⅱのクラス選択です。
専修ゼミⅠ・Ⅱの選択
2年次のゼミは、「世界史専修ゼミⅠ」(春学期)と「世界史専修ゼミⅡ」(秋学期)があります。それぞれ違う教員のクラスを選ぶことができます。
*なお、3・4年次(ゼミⅢ〜Ⅵ)では原則として同じ教員のゼミを履修し、卒論テーマを深めていくことになります。
卒論のテーマについてまだ具体的に決められていない人は、ゼミⅠとⅡで分野の全く異なる教員(例:春学期に中国中世史、秋学期に西洋近現代史など)のクラスを選択して、自分の興味・関心の方向性を見極めてもいいですね。卒論のテーマについて既にある程度決まっている人は、どの教員のゼミに所属すればそのテーマを深められるかを基準に考えましょう。
このゼミⅠ・Ⅱの選択は、2年次生になる直前(3月下旬)に行われるガイダンスの際に、各クラス担当の教員による説明を聞いた上で決めてもらいます。この時にクラス分けがほぼ決まりますので、ガイダンスには必ず出席するようにしてください。
また、2年次の11月から12月にかけての時期に、3年次のゼミⅢ・Ⅳのクラス分けアンケートが実施されます。この時期までに自分の関心のある時代・地域・テーマをある程度絞り込んで、それに近い専門領域の担当教員を選択してください。
2年次に受講すべき科目
ゼミ以外に、2年次に履修すべき科目について説明します。
必修科目
その名の通り、必修です。必ず履修してください。
世界史専修ゼミⅠ(春学期・水曜2限) 世界史専修ゼミⅡ(秋学期・水曜2限)
世界史専修研究Ⅰ(春学期・木曜3限) 世界史専修研究Ⅱ(秋学期・木曜3限)
専修関連科目
世界史専修の皆さんの学びにとって必修科目と並んで大きな意義と役割をもっている科目です。ぜひ履修してください。
世界史専修の専修関連科目については、専修の専任教員あるいは専修が推薦した非常勤講師が授業を担当しています。歴史学研究者による、歴史を学ぶ人たちのための科目であり、世界史専修に分属した学生の皆さんにぜひ履修してほしい科目です。特に、「世界史史料研究Ⅰ/Ⅱ」は、卒論執筆の際に大変役立つ英文や漢文の講読授業ですので、シラバスの内容をよく読んで、積極的に履修してください。2年次では以下の6科目が履修可能で、単位数はいずれも2単位です。
世界史史料研究Ⅰ(春学期・水曜4限) 世界史史料研究Ⅱ(秋学期・水曜4限)
*上記2つの授業はそれそれ2クラス開講(1組:英語/2組:漢文)
世界史研究a(春学期・月曜5限) 世界史研究b(秋学期・月曜5限)
ユーラシア史a(春学期・金曜2限) ユーラシア史b(秋学期・月曜3限)
必修科目・専修関連科目の時間割(2026年度)
以下の表を参考に、2年次の時間割を組んでみましょう。
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
| 1 | ||||||
| 2 | 必世界史専修ゼミⅠ/Ⅱ | 専ユーラシア史a | ||||
| 3 | 専ユーラシア史b | 必世界史専修研究Ⅰ/Ⅱ | ||||
| 4 | 専世界史史料研究Ⅰ/Ⅱ | |||||
| 5 | 専世界史研究a/b |
注意点
上の表は、世界史専修2年次の必修科目と専修関連科目のみあげたものです。共通教養科目、総合人文学科目、文学部外国語科目、他専修の専修関連科目、資格関連科目などはあげていませんので注意してください。
3年次生へ
専修ゼミについて

3年次では、世界史専修の教員全員が演習(世界史専修ゼミⅢ/Ⅳ)を担当します。ゼミでは、各担当教員の指導のもと、少人数のゼミ学生が各自のテーマについて発表をおこない、ゼミのメンバーとの議論を通じて研究を深めていきます。
研究のテーマは、4年次で作成する卒業論文を念頭に置いて決めます。はじめは地域と時代と分野を組み合わせた漠然としたテーマでもかまいません(イギリスの宗教改革、唐代の文化など)。好きな映画や漫画を入口にテーマを探してもよいでしょう。大切なのは、自分が興味を持てるテーマを自分自身で見つけることです。
大まかなテーマが決まったら、参考文献を探し、論点を整理します。参考文献が極端に少ない場合は、関連するテーマが他にないか指導教員に相談しましょう。反対にあまりに膨大な数の参考文献が見つかった場合は(フランス革命、ナチ・ドイツなど)、これまでの研究で議論になってきた問題を参考に、テーマをさらに絞る必要があるでしょう。参考文献がある程度集まり、論点も整理できてきたら、改めてテーマを練り直します。実際に研究を進めていくなかで、徐々に焦点の定まったテーマにたどり着くのが一般的です。
その他の履修科目について
必修科目
卒業の要件として必ず履修すべき科目です。3年次は上で紹介した「世界史専修ゼミⅢ/Ⅳ」に加えて、以下の2科目です。
世界史専修研究Ⅲ(春学期・金曜3限) 世界史専修研究Ⅳ(秋学期・金曜3限)
専修関連科目
必修科目と並んで、歴史を見る眼を養い、実際に文献や史料を読み解く能力を身につけるうえで、重要な意義と役割をもっている科目です。シラバスをよく読んで、積極的に履修するようにしましょう。3年次には以下の10科目が用意されています。特に、「世界史史料研究Ⅲ/Ⅳ」は、研究を進めるのに必要な、英文や漢文の読解能力を鍛える講読授業ですので、ぜひ履修してください。例えば、前近代の中国史で研究テーマを考えている人は漢文のクラス、それ以外の分野でしたら、英語のクラスを履修するとよいでしょう。
世界史史料研究Ⅲ (春学期)
1組:英語(木曜2限)/2組:漢文(火曜4限)
世界史史料研究Ⅳ(秋学期)
1組:英語(月曜4限)/2組:漢文(火曜4限)
西洋史研究a(春学期・月曜2限) 西洋史研究b(秋学期・金曜2限)
西洋社会史a(春学期・金曜4限) 西洋社会史b(秋学期・木曜4限)
アジア史研究a(春学期・月曜5限) アジア史研究b(秋学期・金曜2限)
アジア社会史a(春学期・水曜3限) アジア社会史b(秋学期・水曜4限)
必修科目・専修関連科目の時間割(2026年度)
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
| 1 | ||||||
| 2 | 専西洋史研究a | 必世界史専修ゼミⅢ/Ⅳ | 専世界史史料研究Ⅲ(1組) | 専西洋史研究b 専アジア社会史b | ||
| 3 | 専アジア社会史a | 必世界史専修研究Ⅲ/Ⅳ | ||||
| 4 | 専世界史史料研究Ⅳ(1組) | 専世界史史料研究Ⅲ/Ⅳ(2組) | 専アジア社会史b | 専西洋社会史b | 専西洋社会史a | |
| 5 | 専アジア史研究a |
注意点
上の表はいずれも、世界史専修3年次の必修科目と専修関連科目のみあげたものです。共通教養科目、総合人文学科目、文学部外国語科目、他専修の専修関連科目、資格関連科目などはあげていませんので注意してください。
4年次生へ
専修ゼミおよび卒業論文について
4年次生では(原則として)3年次生のときと同じ指導教員の演習(世界史専修ゼミⅤ/Ⅵ)に所属して、卒業論文を作成します。卒業論文を書くには、焦点の定まったテーマを設定する必要があります。3年次と同様、文献の収集と論点の整理を通じて検討を重ね、最終的なテーマを決定します。具体例は、本ホームページにある「卒業論文」を参照してください。

4年次生では、ぜひ史料の読解にも挑戦してみましょう。たしかに史料を読み解くのはやさしいことではありません。その特性を理解しておくことが必要ですし(必ずしも求めている情報が得られるとは限らず、嘘や間違いがあるかもしれません)、日本語に翻訳された史料はごく少数ですから、外国語(漢文や英語等々)の読解力も求められます。しかし史料には研究文献では味わうことのできない魅力があります。臨場感あふれる現場の声に耳を傾けてみてください。
卒業論文は、おそらく皆さんがこれまでに書いてきたなかで、もっとも長い文章になるでしょう(例年2万字程度)。この分量を論理的に、かつ読みやすく書く技術は、短期間で身につくものではありません。文章を書くことと読むことは、車の両輪のようなものです。整った文章を書くためには、日頃からさまざまな分野の文章にたくさん触れることが必要不可欠です。卒業論文のためだけに、あわてて本を読んでも、他人に伝わるまとまった文章は書けません。その意味では、卒業論文の作成は4年次生になる前から始まっているのです。
卒業論文作成のモデルケース
①「唐代宮女服飾考―図像による検証を中心として―」
歴史の卒業論文は、政治史や軍事史、あるいは経済史といったものがイメージとしてあるかもしれません。ただ、最近では、服装や食事といった文化をテーマにするものも増えています。また、中国史で卒業論文を書く場合、漢文(古典中国語)で書かれた記録(一次史料)をもとに、過去の歴史事実を復元し、それが中国史(あるいは各王朝史)においてどのような意味があったのかを考察し論じていきます。ただ、古い時代では文字史料が少ないため、文字以外の資料を使うこともあります。ここで紹介する卒業論文は、唐代の陵墓から発見された壁画や俑などを利用し、女性の服装について研究したものです。
この論文の著者は、壁画や俑、石槨に彫られた画像、絵画など幅広い図像資料から唐代宮女(宮中に仕える女性)の服飾を調べ、それらを模写し情報を整理しました。その総数は300余りです。このデータから、唐代290年間の時期ごとの服装の流行を明らかにしました。その結果、初唐は細身のシルエットによって醸し出される洗練された健康的なスタイル、盛唐は異文化の要素を取り入れた色鮮やかで大胆なスタイル、そして中晩唐はシックな色合いと太身のシルエットが織りなす優雅で豊満なスタイル、というように移り変わっていったことを明らかにしました。また、唐代には袒胸装や半臂、胡服など、他の時代には見られない自由で多様なファッションがありましたが、それらも図像資料から具体的に裏付けました。著者は、このような服飾が登場した背景として、唐が南北朝時代の分裂を経て形成された多民族王朝であり、また少なくとも八世紀半ばまでは東ユーラシアに君臨する世界帝国であったため寛容な気風がめばえ、そのことが宮女の服飾の開放的な美しさを生み出したのだと結論付けました。
②「イギリス王政復古期の演劇における「女優」の誕生」
この論文は、王政復古期(1660-1688年)のイギリスで職業としての女優が誕生した経緯と、女優の受容をめぐる社会の価値観の変化を追った研究です。これまでイギリス演劇の研究は、シェークスピアが活躍したエリザベス1世時代(1558-1603年)に注目が集まってきましたが、この論文は女優という新しい職業集団の登場に着目することで、従来の研究では等閑視されてきた王政復古期にイギリス演劇の転換点を見出し、これを再評価しようという意欲的な試みです。この論文の最大の特長は、『サミュエル・ピープスの日記』(1660-1669年)という同時代史料を網羅的かつ丹念に読み解いた点にあります。ピープスが10年間に観た劇作品のすべてを整理し、そのうえで、女優について言及した箇所を取り上げ、その評価に関わる部分を詳細に検討しています。そこから17世紀後半にイギリスの観衆が女優を徐々に受け入れ、その演技を楽しむようになった過程が明らかになりました。
カリキュラム
2020年度入学生以降
※以下は世界史専修に関係する情報のみ記載しています。詳細はハンドブック(大学要覧)を参照してください。
初年次導入科目(選択必修科目)
| 授業科目 | 配当年次 | 単位 | 履修上の区分 | 授業期間 | 毎週授業時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学びの扉(各専修) | 1 | 2 | 選択必修 | 1 | 2 |
| 知へのパスポートa(各専修) | 1 | 1 | 選択必修 | 1 | 2 |
| 知へのパスポートb(各専修) | 1 | 1 | 選択必修 | 1 | 2 |
総合人文学科目(選択科目)
詳細はハンドブックを参照してください。「知のナヴィゲーター」は必履修科目です。
文学部外国語科目(選択科目)
「西アジアの言語1/2」「古代エジプト語I/II」など多数開講。詳細はハンドブックを参照してください。
専修固有科目(必修科目)
| 授業科目 | 配当年次 | 単位 | 履修上の区分 | 授業期間 | 毎週授業時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界史専修ゼミI | 2 | 1 | 必修 | 1 | 2 |
| 世界史専修ゼミII | 2 | 1 | 必修 | 1 | 2 |
| 世界史専修研究I | 2 | 2 | 必修 | 1 | 2 |
| 世界史専修研究II | 2 | 2 | 必修 | 1 | 2 |
| 世界史専修ゼミⅢ | 3 | 1 | 必修 | 1 | 2 |
| 世界史専修ゼミⅣ | 3 | 1 | 必修 | 1 | 2 |
| 世界史専修研究Ⅲ | 3 | 2 | 必修 | 1 | 2 |
| 世界史専修研究Ⅳ | 3 | 2 | 必修 | 1 | 2 |
| 世界史専修ゼミV | 4 | 1 | 必修 | 1 | 2 |
| 世界史専修ゼミⅥ | 4 | 1 | 必修 | 1 | 2 |
| 卒業論文 | 4 | 4 | 必修 | ― | ― |
専修関連科目(選択科目)
| 授業科目 | 配当年次 | 単位 | 履修上の区分 | 授業期間 | 毎週授業時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユーラシア史a | 2 | 2 | 選択 | 1 | 2 |
| ユーラシア史b | 2 | 2 | 選択 | 1 | 2 |
| 世界史研究a | 2 | 2 | 選択 | 1 | 2 |
| 世界史研究b | 2 | 2 | 選択 | 1 | 2 |
| 世界史史料研究I | 2 | 2 | 選択 | 1 | 2 |
| 世界史史料研究II | 2 | 2 | 選択 | 1 | 2 |
| アジア史研究a | 3 | 2 | 選択 | 1 | 2 |
| アジア史研究b | 3 | 2 | 選択 | 1 | 2 |
| アジア社会史a | 3 | 2 | 選択 | 1 | 2 |
| アジア社会史b | 3 | 2 | 選択 | 1 | 2 |
| 西洋史研究a | 3 | 2 | 選択 | 1 | 2 |
| 西洋史研究b | 3 | 2 | 選択 | 1 | 2 |
| 西洋社会史a | 3 | 2 | 選択 | 1 | 2 |
| 西洋社会史b | 3 | 2 | 選択 | 1 | 2 |
| 世界史史料研究Ⅲ | 3 | 2 | 選択 | 1 | 2 |
| 世界史史料研究Ⅳ | 3 | 2 | 選択 | 1 | 2 |
資格関連科目等(自由科目)
「東洋史概説a/b」「西洋史概説a/b」など多数開講。詳細はハンドブックを参照してください。