教養科目
関大生として,あるいは社会を構成する一人の人間として,備えておくことが望ましい学問知や社会的知識を幅広く習得する科目です。
- 自己をみつめる(通称:じこみつ)
自己(身体,感情,意識),他者(友情,恋愛,家族),世界(自然,動物,神仏)といったホリスティックで統合的な視点から自分をみつめます。
特に受講生から人気が高いのは「恋愛」の回。科学的な研究の成果を参照しながら,愛について考えます。
専門科目
心理学に関連する科目の他に,1年生を対象とした「アカデミック・スキル」の授業も担当しています。
- スピリチュアリティと宗教性の心理学(3年次生以上)
スピリチュアリティとは,ヒトが生き死にの問題を考えたり,人智を超えた存在を感じたりするココロの働きのことです。
アメリカ心理学会(American Psychological Association)に”Psychology of Religion and Spirituality“部門が設立されるなど,これらのテーマは学術研究の対象となっています。
関西大学文学心理学専修でしか受講できない,そんな授業を創りたいと思っていますが,その筆頭が,当科目です。
『ビッグ・ゴッド』『死者の力』『呪いの研究』といった文献を中心に輪読を行います。
- 教育心理学(2年次生以上)
教員免許の取得に必要な科目ですが,教育や心理に関心のある学生さんも受講しています。
「俺,どうせ頭悪いし,何やっても無駄なんだよ。勉強したくねぇ」。そんな子どもと出会ったら,あなた(先生)は,どのようなサポートをするでしょうか?
この子が,どこでつまずいているのかを見極め,効果的な手立てを考えることが重要ですが,そのためには,発達や学習・記憶,動機づけ(モチベーション)の仕組みや,学級集団のダイナミズム(リーダシップや人間関係)について理解しておくことが有益です。
- 知へのパスポート(1年次生)
2年次生より配属を希望する専修についての,最初の学びです。
「もし,自分たちが学校を創るとすれば,どのような特徴をもった学校にするか?」というテーマでグループワークを行い,全体に向けてプレゼンを行います。
現代の教育問題に対して理解を深めるとともに,その解決策を,主に心理学や教育学のエビデンスに基づいて考案していきます。
- 知のナヴィゲーター(1年次生)
大学での,そして,卒業後も続いてく「学び」に役立つスキルを学びます。
✔︎「調べる」・・・関大図書館には200万冊をこえる蔵書があり,国内上位に位置付けられます。学びの資源である図書館を有効に使うため,各自の関心ある1冊を調べて報告する活動をします。
✔︎「読む」・・・関大には「新入生に贈る100冊」という素晴らしい企画があります!リストから1冊を選んで内容を要約し,グループでディスカッションを行います。
✔︎「書く」・・・レポートの『型』(例:パラグラフライティング,5段落論証)を学びます。まずは,「私を漢字一文字で表すと?」というお題で練習し,学校の働き方改革に沿ったテーマで本レポートを仕上げます。
✔︎「発表する」・・・『心理学的に正しいプレゼン』という書籍を全員で分担し,1人1回スライドを作成して発表します。ルーブリック評価という手法を用いて,発表者には,受講者全員からフィードバックが行われます。
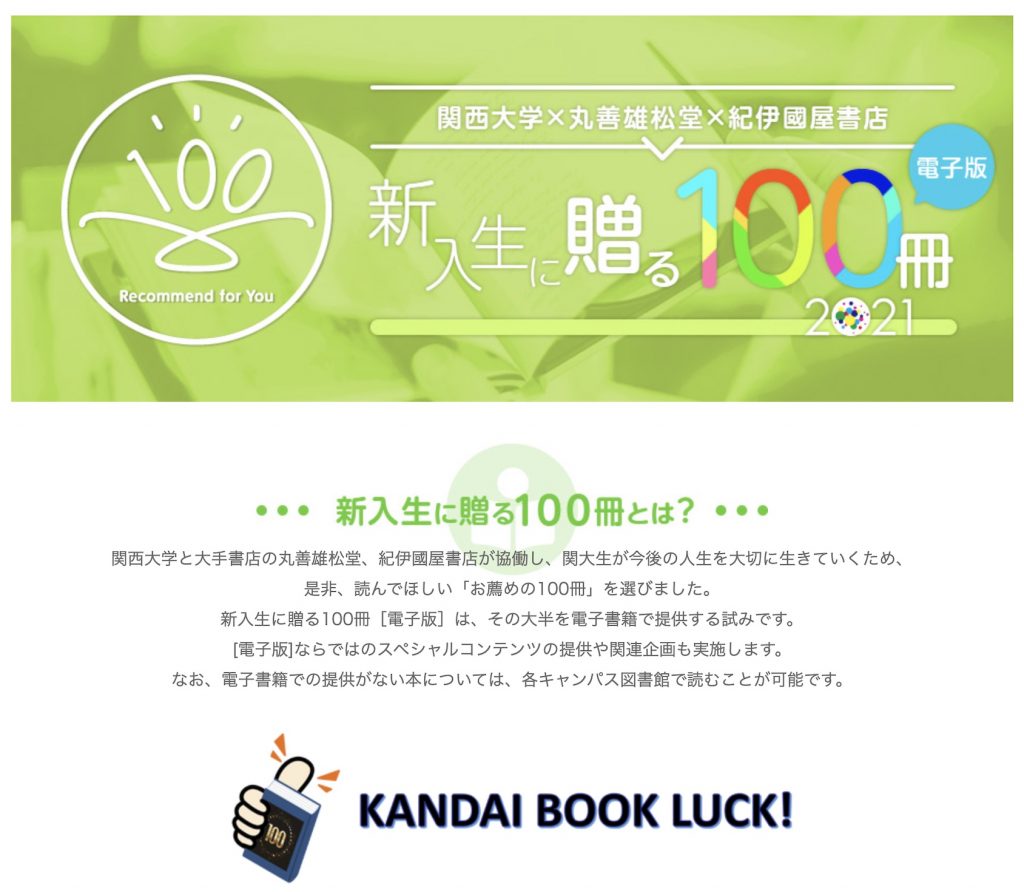
ゼミ活動
文学部心理学専修では,自分に合ったラボ(ゼミ)を選択できるよう,2年次から「プレゼミ」制度を導入しています。3,4年次は,配属されたラボ(「本ゼミ」)で卒業研究を進めていきます。村上のラボでは以下のような活動を行なっています。
- プレゼミ(2年次)
前半では,自分や世界とのつながりを再構成するホリスティックなワークを,ゼミ生自身がファシリテーターとなって進めていきます。例えば…
・自分とのつながり:現在と未来のボディ・イメージをドローイング,名前の由来を調べ想いをデザイン,夢マップ
・他者とのつながり:感謝の手紙,ロールレタリング,コンセンサスを得る方法
・世界とのつながり:NIMBY,未来のタイムライン,学校を10倍楽しくする方法
後半では,卒業研究の第一歩として,文献発表を行います。テーマは自由。自分が心惹かれた学術論文をパワーポイントにまとめて発表し,みんなであれこれ意見交換を行います。研究の成果や課題,発表者独自の視点での考察も述べ,卒業研究のタネを探します。

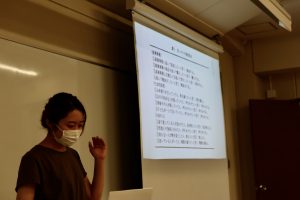
- 本ゼミ(3,4年次)
3年次春学期には,輪読を通じて「ビッグ・クエスチョンズ(人生の意味等)」に向き合い,研究のタネを見つけていきます。秋学期からは,関心テーマについて書かれた学術文献を調べ,研究計画を発表します。ゼミ生や村上とディスカッションを重ね,徐々に自分の問題意識を明確にしていきます。
関心の芽は人それぞれ。日常の何気ない一コマ,自分の悩み,友達や恋人のこと,授業で聴いた面白い話…。たくさんのゼミ生とやりとりしてきましたが,誰一人として同じテーマになることはなく,それぞれのカラーが出るものです。卒論を通じて,自分をみつめていきます。
テーマが固まり,問題の背景や目的(仮説)が整理できた人から,調査や実験を行い,分析し,卒業論文としてまとめていきます。媒介分析や階層的重回帰分析といった量的な手法を主に扱いますが,インタビュー等の質的研究や,レパートリー・グリッド法(Repertory Grid Technique)を使用した卒論生もいます。
卒業研究を通じて,自分で問題を発見し,最適な方法を用いて,最適解を導き出す,という力をみにつけてほしいと思っています。卒業後,それぞれのフィールドで生きていくわけですが,その場を少しずつ良くしていくために,これらの力がきっと役に立つからです。