このブログをはじめたきっかけは、たしか2018年の世界新教育学会に参加したことだったと思う。朝日大学の足立淳先生のブログを拝見させていただき、「難しいものではないよ」と背中を押してもらったことが力になった。本当は自分でコードを書けばよかったのだけれど、忙しさにかまけて有料のWixを利用。それでもブログがあったおかげで、コロナ禍の遠隔授業にも急遽対応することができたし(大学のラーニングシステムはアップロードできる容量が小さく、動画を挙げるのに制限がある場合が多い。)、学生や研究仲間とのつながりの場を増やすこともできた。ほんと、初対面にもかかわらず丁寧に教えてくださった足立先生には感謝の他ない。
そして、その足立先生から先日、ご研究の成果物をいただいた。
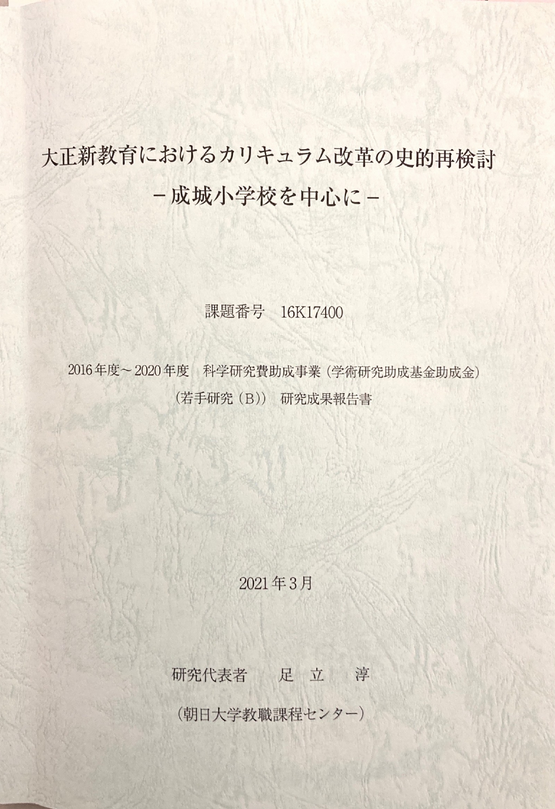
若手科研の報告書「大正新教育におけるカリキュラム改革の史的再検討−成城小学校を中心に−」だ。むむむ。素晴らしい。僕は普段ブログにおいて、読んだものをまとめたり、意見を書いたりすることはないのだけれど(ふつう、研究者のブログではしばしば、そのような営みが発信される。)、今日はそれをしてみようと思う。
報告書は5本の論文からなる。
第一の論文は「赤井米吉の教育思想における西田哲学の影響−両者の『自覚』概念の同質性に着目して−」である。タイトルに明示されているように、「大正新教育の旗手」たる赤井米吉の教育思想の重要な位置を占める「自覚」概念が、西田幾多郎の自覚論の枠組みに則って展開されたものであることが論じられる。本論文によれば西田における「自覚」とは、「唯一の実在である『純粋経験』が無限の矛盾と統一とによって発展していく構造(=『自覚的体系』)を指すと同時に、その統一の極地としての理想的境地(=『絶対自由の意志』)をも含意していた。後者は、端的に『神の意志』と換言されもするし、真善美といった諸価値が『宗教』において一致する境位とされもする」(p.6)もので、これを教育論に落とし込んだ結果、「『自由』と『協同』、『教授』と『学習』といった様々な矛盾を展開の契機とし、それらを『人神共同』の境地において統一しようと企図するもの」(p.7)となった。「人神共同」とは、赤井の言う所の「自由」が「協同」と一致する境地を示す言葉である。
教育の構造を弁証法的運動として示すと同時に、その目的論をも含みこむ赤井(=西田)の教育思想には非常に共感するところがあった。僕が『芦田恵之助の教育思想』で描こうとした彼の教育思想にも、「固定的な世界認識にとらわれることのない、絶えざる認識の更新」が根底にあったからだ。
第二の論文は「1930年代初頭新潟における子どもの生活世界と『戦争』−児童文集を手がかりとして−」である。非日常として描かれがちな「戦争」を日常の視点から問い直すために、1930年代の新潟における児童文集を訪ねる試みだ。当時の言説空間の形成に寄与したであろう主要なメディアである新聞の記述に着目したのちに、満州事変前後の子どもの作品が分析される。
分析対象は中蒲原郡中部作文の会によって発刊された『綴方文集』である。1930年6月から1933年3月までのものが残存し、不定期ながら中蒲原郡中部(現・新潟市秋葉区)に属していた小学校の子どもの作品が掲載されている。「同会がどのような経緯で設立され、いつからいつまで活動したのか、どのような性格や思想を有する教師たちの意図によってこの文集が編集されたのか、詳細は不明」(p.14)ながらも、同作文の会は「教育理念を共有する有志の教師たちによる私的な団体であったというよりは、何らかの公的な性格を帯びた組織であった可能性が高い」(同上)という。
同文集では、「1930年6月号から1931年10月号までは、軍隊や満州などに関する子どもの文章はほとんど見られ」(同上)ない。「子どもたちの対外的な敵意が剥き出しにされた文章が一挙に増加」(p.16)するのは、満州事変勃発直後に編集されたと見られる1931年12月号以降である。論文では次の文章が挙げられていた。
戦争のこと
小須戸校 井上ミツ
今、日本としなが満州で戦争をしてゐるのです。お夕飯がすんでからよ(ママ)お父さんが「日本がきつと負けるかもしれない。」とおつしやいました。私はその時、しなゝんて一ぺんにころしてくれたいと思ひました〔。〕
昨日の夕方、赤ちやんをおぶつて新聞屋の前へ行くと、戦争のしやしんが、出てゐるのか、しやしんを見てゐました。
私はうちに居ても、学校に居ても、日本が勝つといゝがなあと思つています。
今頃兵たいさんはどんなにしてゐるでせう。
ほんとに兵たいさんはかはいさうです。
評 かざりけのないまごゝろのこもつた文。
(p.18)
この文章からは、「敵愾心や愛国心や同情心が、教師による『かざりけのないまごゝろ』との評価によって承認されていく構図が浮き彫りにな」(同上)っている。戦争が苛烈さを増すに従い、子どもの文章もまた戦争へと接近してゆく。もちろん、これらの作品は「あくまでも教師をはじめとする、おとなの目に触れることを前提として作られたものであ」(p.19)り、「私的な場面で認められた手紙や日記などとは違って、教室という公的な環境で教師の指導のもとに綴られた文章は、多かれ少なかれ、大人たちが子どもに期待する規範を内面化したもの」(同上)となっている。川村湊が『作文のなかの大日本帝国』で明らかにしたように、ここに「忖度する主体性」を見出すことも可能だろう。重要なのは、作文を通じた大人の規範的価値への同一化が、戦争を「陳腐な『日常』への一場面へと埋め込」(p.20)む装置として機能したということである。また他方で、子どもたちは出兵の見送りという「儀式」によって非日常としての「戦争」を体験し、そのことを作文によって内面化していた。
以上のような、当時の子どもの生活作文の分析は、読者にある種の想像力を要請する。それは、固定的な「戦争」のイメージを打ち破り、「日常」との連続の中にある「戦争」に思いを馳せる力である。
第三の論文は、「1930年代初頭成城小学校における小林茂の教育論に関する基礎的研究−その郷土地理教育論に着目して−」である。論文の冒頭には次のような目的が掲げられている。「本稿は、1930年代初頭の成城小学校における教育研究の到達点と限界性を解明するための史的研究の一環として、当時の同校の主力教師の一人であった小林茂が展開した郷土地理教育論について検討することを目的とする」と。
小林茂は青山師範学校専攻科にて永井芳夫に指示した人物である。アメリカのカリキュラム改革に学び、それが小林の思想形成にも影響を与えた。さらに、小林の思想形成にはマルクス主義も大きな影響を与えている。ただし、「プロレタリア教育運動に身を投じた形跡」(p.31)は無く、小林はあくまで「人生の意義の探求」に資する「歴史的法則」の一つとしてマルクス主義を捉えていた。小林の立場の根本には「人格主義」、それも「当時の人格主義」よろしく、「国家の『人格』を実体視しつつ、個人の『自覚』を通じた『人格』の実現を、国家のそれを完成させるための方途として位置付けようとする傾向」(p.31)が強かったという。本論文は、この小林に着目することで、従来の研究で等閑視されていた沢柳亡き後の成城小学校の教育研究の実態を解明しようとする意欲的な試みである。
1930年、横川尋常小学校から成城小学校へと転任した小林は、やがて「郷土地理教育」の理論と実践を展開していく。「日本の教育界では郷土教育が注目を集めつつあった」(p.32)当時にして、しかしその「郷土」の概念は曖昧であった。小林はこれにチャレンジしていく。足立先生によると、小林が初めて「郷土」概念自体を考究の対象に据えたのは、1931年4月の「郷土地理の取扱について」であった。
同論考で小林が示す「郷土」とは、「『生活と没交渉』で『概念的な知識の研究』に陥った『社会科学』としての地理学を『社会化』するための基盤であると同時に、『教育具体化』や『教育実際化』と『不即不離な関係』にある地理教育の鍵概念としても期待されるものであった」(同上)。ざらざらとした、理論化以前、すなわち言語化される前の「生活」の供給源として「郷土」に着目したのだろう。この観点から、小林は1932年、その教育課程の構想を記した『郷土地理教育論』を刊行する。
足立先生は、「小林の郷土地理教育論は、『成城学習』の諸要素を自らの教科課程論や教育方法論の中に構造的に位置付けた点において、『生活の社会化』という新たな研究方針に基づいて展開した1930年代初等成城小における教育研究の一つの到達点を示すものとして位置付けられよう」(p.36)と述べる。急ぎ注釈が加えられているのは、小林の「国際主義」の立場と「国家的自覚」という「自家撞着に陥っていた点に限界性を見ることができ」(同上)るという点である。
成城小学校は言わずと知れた私立学校であるが、健全なナショナリズムがローカリズムに繋がり、それがまた健全なインディビジュアリズム、インタナーショナリズムやコスモポリタリズムに繋がるような教育構想は、当時にとっても重要な課題であったのだろう。この問いに先鞭をつけた論者の一人として、小林を眼差して見たい衝動に駆られた。
(第4、第5論文につづく)