【開催報告】防災×ビジネス×まちづくり ~しなやかな大阪梅田を創るためのトークセッション~【うめだ防災フェス】


2025年4月12日(土)、関西大学梅田キャンパス8階ホールにて、「防災×ビジネス×まちづくり ~しなやかな大阪梅田を創るためのトークセッション~」を開催しました。南海トラフ地震への備えを出発点とし、地域経済の持続や都市のレジリエンスを考える本イベントは、うめだ南海トラフ研究プロジェクトの一環として企画されたものです。
当日は、事前申込を上回る多くの来場者でにぎわい、防災や都市のあり方への関心の高さがうかがえる一日となりました。
■ 開会挨拶 ― 知の拠点としての梅田キャンパス

関西大学梅田キャンパス長の安部誠治氏より、開会の挨拶がありました。
大学はもともと「街に開かれた知の場」であり、市民とともに未来を考える拠点であると語られました。梅田キャンパスには3日間分の備蓄が整備されており、災害時の避難所としての機能を果たす準備があること、また社会安全学部が防災・減災研究のフロントランナーとして活動していることも紹介されました。
■ 基調講演① ― 小澤守氏「巨大災害と都市の責任」
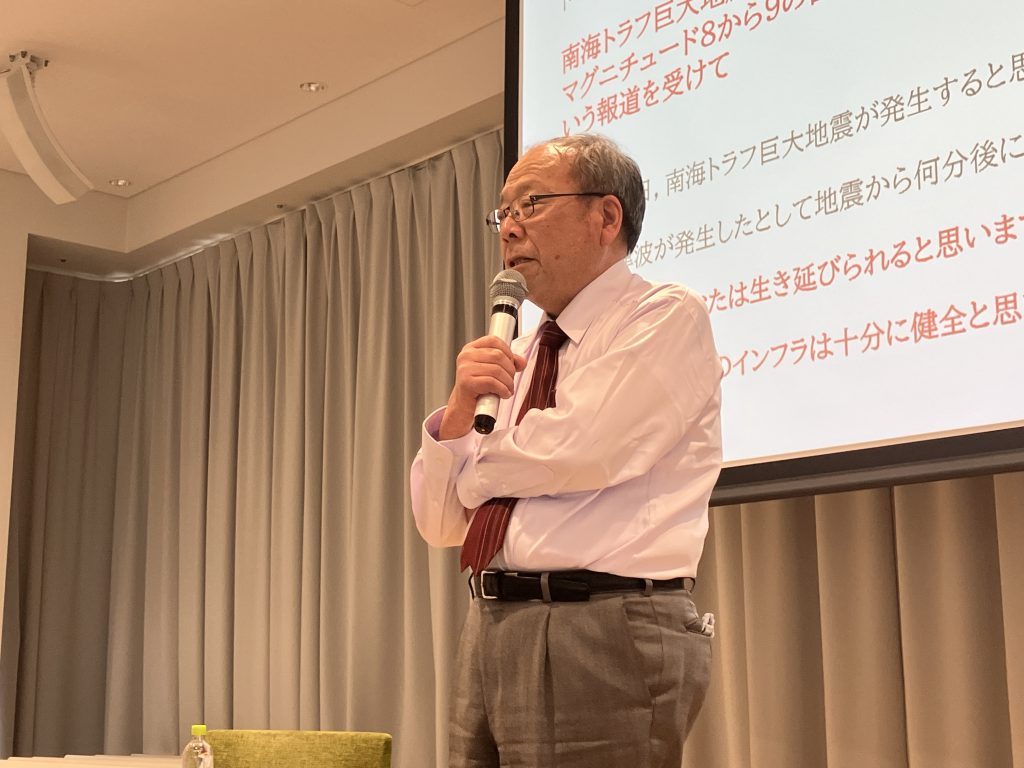
関西大学名誉教授・小澤守氏は、南海トラフ巨大地震の発生確率が「80%程度」とされていることを踏まえ、
「今日、地震が起きると思いますか?」
「津波は何分後に大阪に到達するかご存じですか?」
「あなたは生き延びられますか?」
と問いかけ、これは行政,企業だけの問題ではなく,我々市民みんなの問題であると参加者の防災意識に揺さぶりをかけました。
また、東京一極集中の脆弱性に言及し、「大阪には首都代替機能があるのか」という視点から、文化・経済・人命を守る都市構想の重要性を提起しました。
■ 基調講演② ― 奥村与志弘氏「防災が引き出す地域・企業・人の魅力」

うめだ南海トラフ研究会代表・奥村与志弘からは、御堂筋沿道のビルが津波避難ビルに指定されていない現状や、制度的な課題を指摘した上で、災害時に活用可能な都市空間のポテンシャルについて言及がありました。
また、自身が委員として参画している政府の南海トラフ地震新想定被害についての知見も共有し、「防災が社会課題を炙り出し、地域や企業、そして人の可能性を引き出すきっかけになりうる」と語りました。
■ トークセッション ― 梅田の奇跡と共に歩む仲間たちへ


トークセッションは、地域防災活動に長年携わる山田摩利子氏の進行によりスタート。
山田氏は「既存の防災活動に限界を感じている人は多い。研究会の掲げる“梅田の奇跡”とは?」と問いかけました。
代表の奥村は、研究会が目指す姿として「経済を止めずに命を守る」都市像を提示。南海トラフ地震のような巨大災害に際し、経済・暮らし・安全を両立させるまちづくりの必要性を語りました。
また、現在進行中のデジタルツインの活用についても紹介。研究者・企業・自治体が同じ都市データを“共同注視”することで、災害リスクの見える化と、連携による対応の深化を図る実践が進んでいることが紹介されました。
山田氏からは、「市民もこの取り組みに仲間として関わりたい」との声が上がり、奥村は「“梅田の奇跡”に伴走してくれる仲間がこれから増えていくことを期待している」と応じました。
■ 学生団体や地域団体の参加でにぎわう会場
会場では、大阪市北区役所からは避難所、避難生活体験ブースや梅田東子ども会(梅田東地域活動協議会)、食品メーカーからは非常食の商品展示・試食のブースのほか、関西大学の学生団体も参加。
社会安全学部公認団体KANDAI DPEによる「防災ボトルづくり&防災射的」や、関大万博部による「非常食アレンジ」などの体験型企画が、子どもたちや親子連れで賑わいを見せました。
明るい子どもたちの声が響く中で、専門的な防災議論が展開され、「街と共にある学びの場」としての梅田キャンパスの姿が体現された一日となりました。
トークセッションを進めていただいた山田摩利子氏からも当日の様子をレポートいただいています。
リンク:一般社団法人うめらく うめだ防災フェスin関西大学梅田キャンパス を終えての感想







(文:うめだ南海トラフ研究会)

