第12回研究会(先端科学技術シンポジウム:セッション発表)を開催しました
2025年1月24日、関西大学千里山キャンパスにて「第12回うめだ南トラ研究会」を開催しました。
今回も各分野から多くの研究者や関係者が集まり、南海トラフ地震への備えに関する最新の知見が共有され、活発な議論が交わされました。今回の研究会では、特別講演として、日本放送協会(NHK)大阪放送局の藤島新也氏、ゼンショーグローバルファストホールディングスより、グローバルファスト管理部 営業総務室 室長の松井俊典氏をお招きしご講演いただきました。

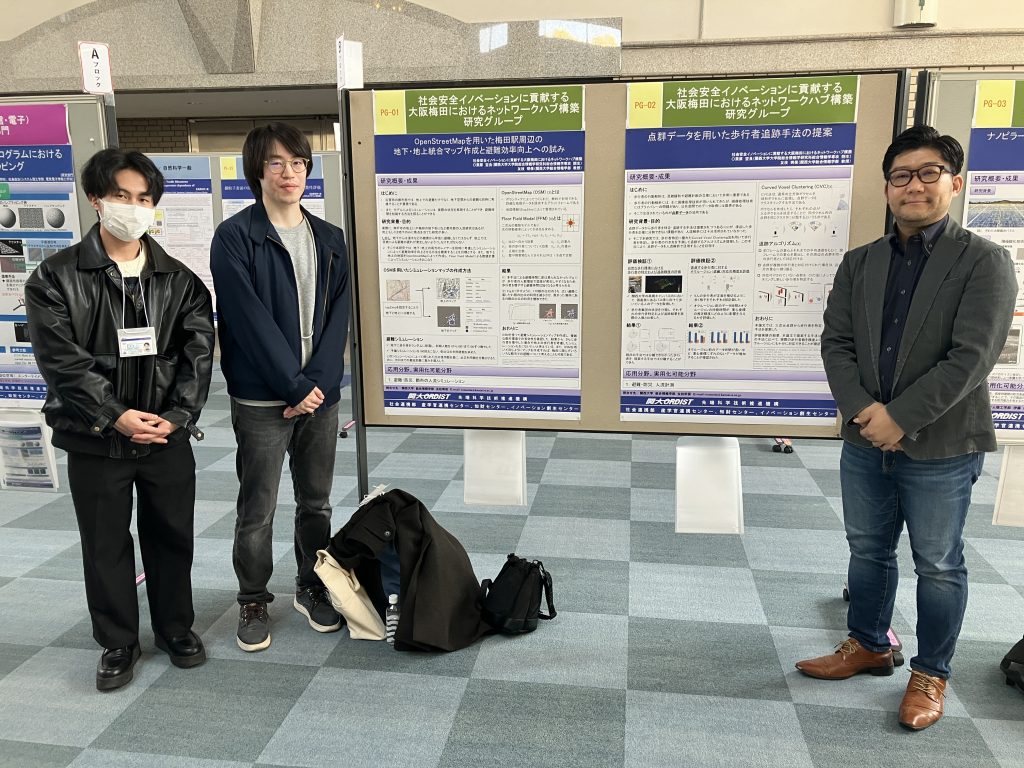

〔招待講演〕
「大阪・梅田における南海トラフ巨大地震対策の課題と展望 ―報道記者の観点から―」
藤島 新也(日本放送協会 大阪放送局)
藤島氏は、東日本大震災での豊富な災害取材の経験をもとに、大阪梅田地区における南海トラフ地震のリスクについて詳しく説明しました。特に、津波の浸水想定が最大2メートルに及ぶことや、大阪駅周辺の被害リスクの高さに焦点を当て、都市部特有の課題を浮き彫りにしました。
津波がビルの間を抜けて想定外の方向から襲う可能性があることを指摘し、現行の避難計画の課題として、避難ビルのキャパシティ不足や地下街からの脱出が困難である点を挙げました。さらに、30センチ程度の水深でも狭い通路では人が流されるほどの水圧が発生することを、自身の水流実験を通じて説明しました。
また、ホワイティ梅田で実施された避難実験では、津波到達想定時間の2時間以内で地上に避難できることが証明されたが、地上に上がったとしても、道路には多くの落下物や人流があることを考慮すると実際にはスムーズに避難できないだろうと説明され、標識や避難誘導策の改善が急務であることが示されました。最後に、NHKとしてのメディアの責務についても言及し、NHK内でもまだまだ認識不足であり、防災に対するさらなる発信力の強化が必要であると結論付けました。

〔招待講演〕
「社会課題への取り組みとその意義―災害支援を事例に―」
ゼンショーグローバルファストホールディングス グローバルファスト管理部 営業総務室 室長)
松井氏は、ゼンショーホールディングスが展開する防災支援の取り組みについて紹介しました。特に、能登半島地震における炊き出し支援の事例を挙げ、キッチンカーを活用した迅速な食料提供の重要性を強調しました。同社は、災害発生直後の断水や物流の途絶といった困難な状況下でも、継続的に支援を行える体制を整えていると紹介されました。
今後の課題として、キッチンカーの増設(平時でも店舗として稼働)やNGOとの連携強化による支援力の向上を挙げ、被災地に対する長期的なサポートの重要性を指摘しました。また、社員の防災意識の向上が、迅速な対応力の強化につながることを強調し、企業としての社会的責任を果たす姿勢を示しました。
同席されていたゼンショー中央研究所所長の永井大氏は、「人類社会の安定と発展に責任を負い、世界から飢餓と貧困を撲滅する」という企業理念に基づいた活動であると説明されました。災害時の支援は特別なものではなく、平時と同じ状況を提供することが使命であると話されました。
また、講演内で紹介されたキッチンカ―も展示いただきました。

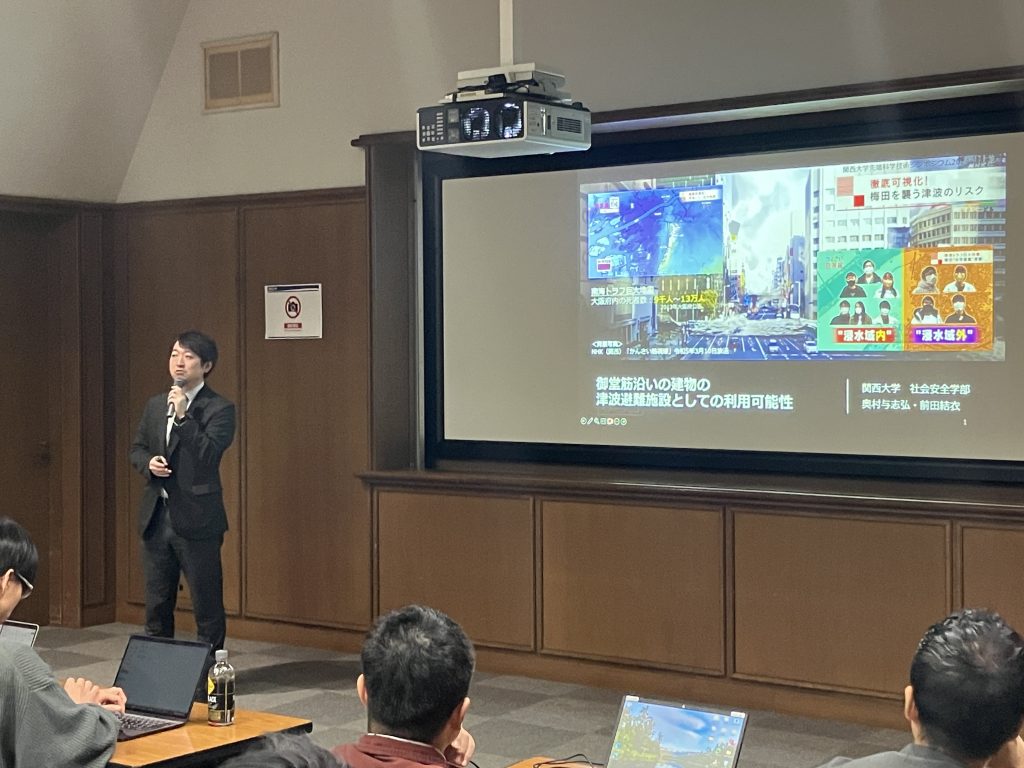
〔講演〕
「御堂筋沿いの建物の津波避難施設としての利用可能性」
奥村 与志弘(『南海トラフ巨大地震を見据えた大阪梅田地区の安全・安心イノベーション』研究会代表)
本研究会の奥村は、梅田周辺の土地勘がない学生を対象に、避難行動の実験を実施したことを紹介しました。この実験では、2時間以内に避難行動したものの、新御堂筋より東側の避難が推奨されていたにもかかわらず、ほとんどの学生が津波想定域外から移動できませんでした。
今後の課題として、都市防災のためのサイン整備の重要性を指摘し、避難ルートや安全エリアの明確化によって、災害時の迅速な対応を可能にする必要性を強調しました。
奥村は、防災対策が地域の経済成長や魅力向上に寄与する可能性を強調しました。現在進めているデジタルツインを活用して平時、災害時の人流や水流、さらにお金の流れをも可視化し、防災インフラの整備や新しいサービスの開発を通じて企業の投資意欲を高め、防災意識の高い街としてのブランド力を強化できると述べました。
〔ポスターセッション〕
今回のシンポジウムでは、当研究会メンバーである関西大学総合情報学部・友枝明保研究室から2点のポスターが発表されました。
少しずつではありますが、人流調査の活動やデジタルツイン整備に向けた研究活動が進行しています。今後もこのような機会を設け、研究成果を発表する場を提供していきたいと考えています。

