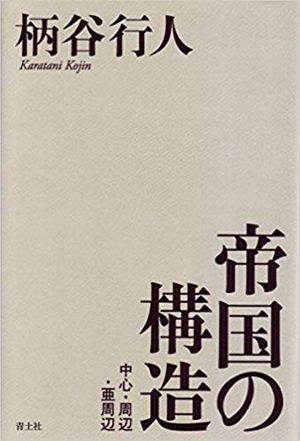
日本教育学会に参加するために行った仙台で、たまたま出会い購入したのが本書。
著者の「あとがき」によると、『世界史の構造』で十分論じることができなかった問題を取り扱ったのが本書『帝国の構造』であり、その目的は大雑把にいえば近代国家を理解する手がかりをつかむことにある。近代国家は旧世界帝国の解体の結果生じたものである。そのため進歩史観において旧帝国は否定的に考えられるが、そこには近代国家には無い要素があり、真に近代国家を乗り越えるためにはそれを改めて検討しなければならない、というわけだ。
僕にとって非常に面白かったのは、「帝国」と「帝国主義」を原理的に異なるものとして分類し、さらに「国民国家」との関係を明快に分析していた点だ。柄谷は次のように述べる。
帝国は多数の民族・国家を統合する原理をもっているが、国民国家にはそれがない。(中略)国民国家が拡大して他民族・他国家を支配するようになる場合、帝国ではなく「帝国主義」となる(pp.85-86)
では「帝国の原理」とはなにか。それは「多数の部族や国家を、服従と保護という『交換』によって統治するシステム」(p.86)である。これだけ読むと、帝国は帝国主義よりも良いもののように思える。なぜなら、帝国の拡大は征服によってなされるが、それは「征服された相手を全面的に同化させたりしない」(同上)からである。しかし、帝国に対して帝国主義は、ネーション=国家の拡大として存在するものと柄谷は言う。つまり帝国主義は「周辺」に対して同化を強要するのだ。
イスラエルを訪れたばかりの僕には、イェルサレムに住むアラブ人が想起されてならない。ダニエル・ゴーディス(ダニエル・ゴーディス著、神藤誉武訳(2018)『イスラエル: 民族復活の歴史』ミルトス。)が仔細に語っているように、占領は誰にとっても重荷なのだ。奇しくもひと月程前、イスラエルをユダヤ人国家であると定める新法が可決したばかりだ。
大学で講義をしていると、日本を「単一民族の国家である」と考える学生が多いことに驚かされる。土地柄もあるかもしれないが、近い将来、いやもう既に、「日本人とは誰か」という問いを、切実なものとして考えなければならない時がきているのかもしれない。