授業をしていて葛藤がある。その一つが遅刻の取り扱いだ。1限の授業を担当していると、時には遅刻してくる学生もいる。しかし僕には、遅刻のバックグラウンドが分からない。アルバイトを遅くまでやっているのかもしれないし、サークルの飲み会だったのかもしれない。家族が事故に遭って夜通し付きっきりだったのかもしれないのだ。
そんな遅刻者たちに、ペナルティを求める学生がいる。「私は早く来てちゃんとしているのに、遅れて来る学生と同じ評価であるのはおかしい」というのだ。彼女らは学校で「関心・意欲・態度」(評価規準における関心・意欲・態度は平成3年の指導要録より重視された)を評価されてきた世代である。僕もそうなので、心情的には共感できる。遅れて来る子は、態度がなっとらん、というわけだ。僕の授業の到達目標には「関心・意欲・態度」に関わる項目はないが、授業を「きちん」と受けなければならないという意識は、強烈に内面化されている。
もちろん、遅刻に対してペナルティがないわけではない。大学の教務規定には、遅刻や早退が3回あると、1回の欠席扱いとなる。しかし教員は、彼女らを監視し、管理し、監督するために教壇に立っているのではない。彼女らは幸せに生きることを望んでおり、その手段として大学に来ている。そして、幸せになる手段として教員免許の取得を目指している。授業はその手助けの一側面であって、少なくとも僕は、決して彼女らに強制的に何かを学ばせようなどとは思ってはいない。だから「遅刻者に対して厳しく接して欲しい」という要望に困惑してしまう時がある。
遅刻に対する罰則などを考える前に、もっと彼女らのペースで学習できるシステム作りができないだろうかと思う。はじめに遅刻の可能性をいくつか挙げたが、遅刻の原因として最も多いのは「朝に弱い」ことだ。自分でカリキュラムを組むことができる点が大学の特性である。しかし、資格を取ろうと思うと必修が多くなり、授業選択の自由度が下がってしまう。朝が苦手な人も1限を取らなければならない。加えて僕の授業の多くは、受講者が100名近くいる一斉授業である。同一の学習内容、同一の空間、同一の時間という制限の下学習することを強いる。自分のペースで自由に学習できたら、もっと効率よく内容を修得できるのに、と思う学生もいるはずだ。この点に関しては学びの個別化に賛成する。これはシステムの問題なので、教員や大学、ひいては社会の課題でもある。
ただし、大学も本質を見失っているわけではない。授業の到達目標をクリアしさえすれば、3分の2回以上の出席で単位を取ることができる。つまり15回全て遅刻しても、単位を取得することは制度上可能なのだ。学びを義務にすることほど、学びの効率性を下げるものはないと思う。
そもそも学問はめちゃくちゃ面白いので、義務的に学ばせる必要なんてない。少なくとも僕にとっては、ラグビーやトライアスロンなどの各種スポーツ、一時期熱狂的にハマった各種のアウトドアに匹敵するくらい面白い。だから、問題があるとすれば遅刻やそれを厳しく取り締まらないことにあるのではなく、面白いはずの学問をうまく伝えられていない僕の方にあるはずだ。「遅刻を厳しく取り締まってください」と聞くと、彼女の要望を叶えてあげたい気持ちと、そうすることで自分の不甲斐なさを肯定してしまうぞという気持ちで葛藤が生じる。
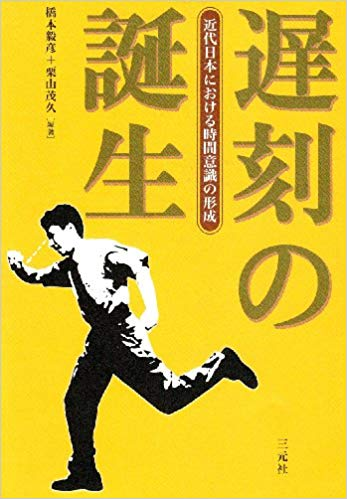
※画像の著書は記事とは直接関係はないのだけれど、「遅刻」を考えるのにとっても良いので転載させていただきました。主題と副題もキマっていて惚れ惚れする。