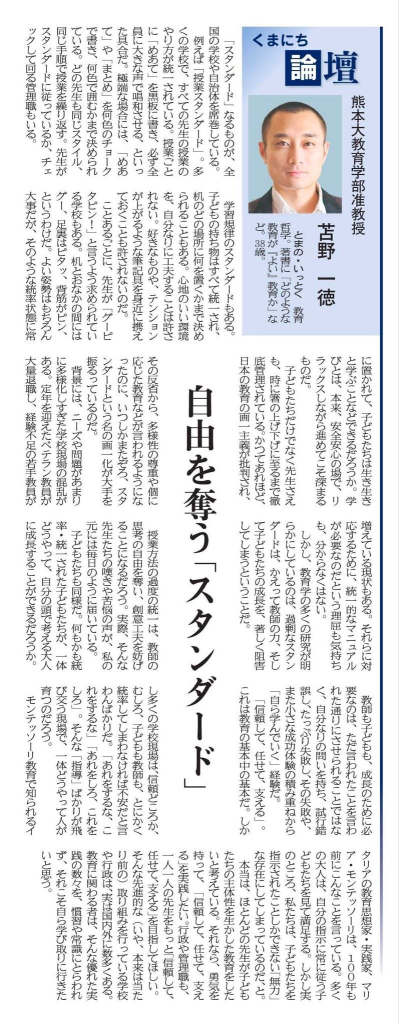元号の改正を3カ月後に控えた2019年2月、高校ラグビー部時代の監督が新天地へ転任するということで、卒部生が広島に集まった。2019年といえば、昨年の小学校に続き中学校でも道徳が「特別な教科」となり、大学の教員養成においてもコア・カリキュラムに基づく新課程が始まる年である。国家による教育の標準化・画一化の浸透が懸念される昨今において、人を通じた教育とは何かを考えさせられる出来事だったので書き記しておきたい。
母校のラグビー部は2002年の創部以来、13回の全国大会出場を誇るいわゆる強豪校である。17年の歴史の中で自宅から通学する部員は例外中の例外であり、ほぼ全ての部員が寮生活を通じて寝食を共にする。文武両道を掲げ、ラグビーを基盤とした全生活による人間形成が目指されるため、部員には学校の枠組みを超えた学びや成長が期待されている。
その共同体を創設し、牽引してきた先生の転任である。120名を越すOBが一堂に会し、泊まりがけで先生に感謝を述べ、グラウンドで在学生や世代を超えた卒業生らと交わった。遠くから足を運んできたOB、家族連れのOBもたくさんいた。かなり無理をして集まった者も多かったに違いないが、皆一様に晴れやかな顔をしていた。私もそうだったが、日頃の苦労を忘れ、夢を追いかけた高校時代を思い出し、明日からの活力をもらったからだ。

そうして120名を超える人々が集まったのは、あの監督、あのコーチの下で、あのメンバーで高校時代を過ごしたからに他ならない。決して代えのきかない出会いがそこにはあった。奇しくも監督は、卒部生を含めた教え子たちに、最後に「邂逅」という言葉を残した。

邂逅とは、思いがけない偶然の出会い、つまりかけがえのない一回性の出来事に使われる言葉である。教育は、とりわけ知識や技能の教育(陶冶: Bildung)にとどまらない意思や情念の教育(訓育: Erziehung)は、余人をもって代え難い人々によって初めて可能となる。ラグビー部時代には辛く悔しい目に遭ったこともあるが、彼らのほとばしる情熱やより良いものを求める意志ゆえに、僕はラグビーを嫌いになることはないだろう。そればかりでなく、人というものに絶望することもないと思う。


教育界に対し、説明責任の一環として質保証がやかましく求められているが、教育は決して標準化・画一化によって達成できる領域のみで構成されている訳ではない。それは、確かに教育作用と被作用の関係があまりに包括的であるがゆえに、目的合理的に因果関係を実証できないものであるとしても、「人(教師や仲間の人間性)を通して」行われるものである。そうであるとすれば、生活指導を完全に排除して教科指導が行えるものであるとする言説や、道徳を、学校の、しかも教科の領域に閉じ込めておけるかのような考えには、疑問を抱かざるを得ない。意志や情念の教育は、一人一人の日常の生活の中で、他者との関係においていかに生きるかという葛藤の中で育まれるものだからである。
※教育の標準(スタンダート)化については、苫野先生の下記の記事を参照してください。