2025年度研究室メンバー
博士後期課程
D3
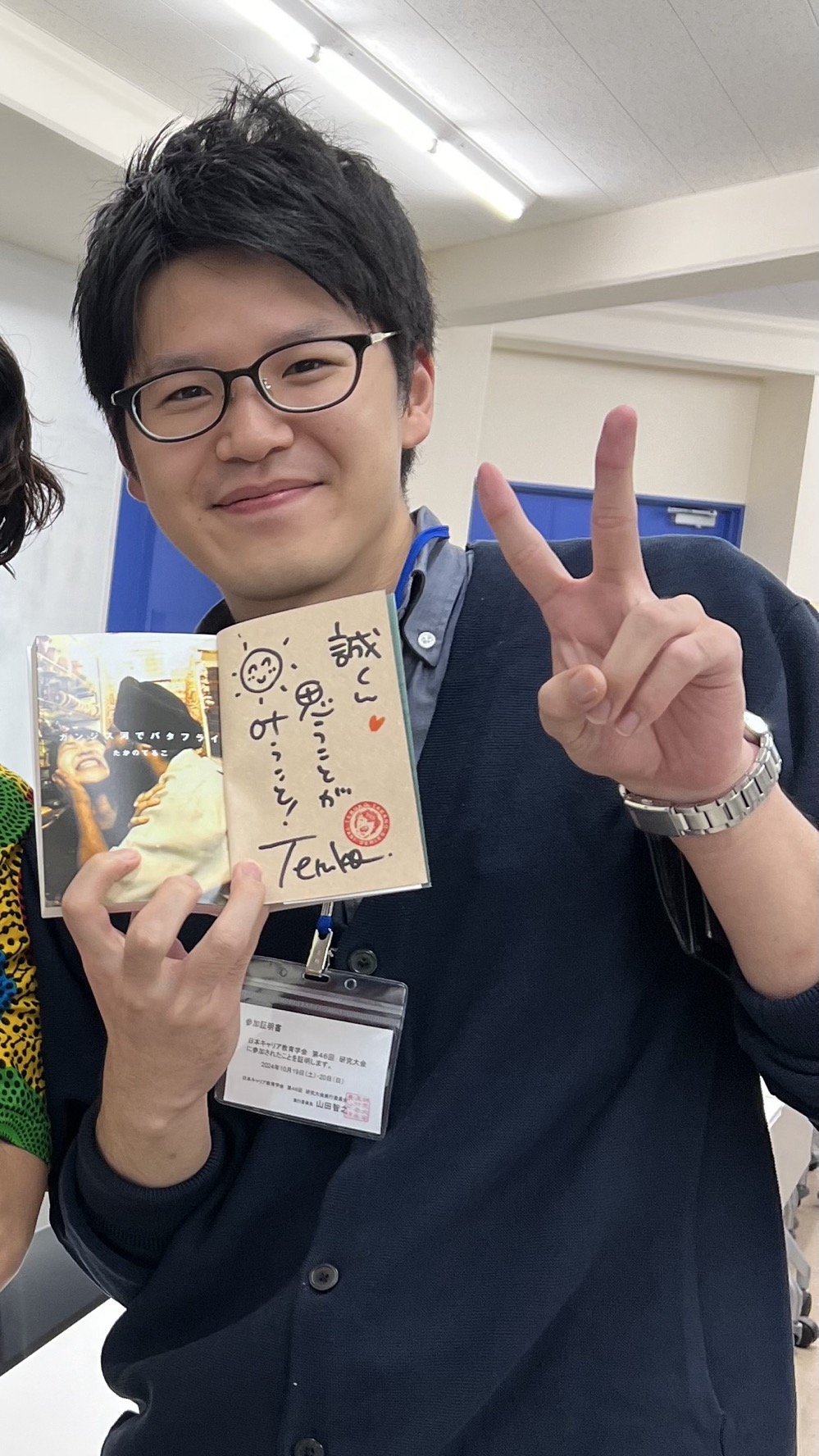
| 名前 | 中大路 誠(NAKAOJI Makoto) |
| 学年 | 博士課程 後期課程 3年 |
| 研究内容 | テーマ:データサイエンス学習に対する認知的興味の形成メカニズムの解明 学習する際に、興味は重要な役割を果たすと考えられています。しかし、ほとんどの学生は、勉強することをおもしろいと思えていないようです。特に近年重要視されるデータサイエンス学習において、興味をもって取り組めていない学生がいることは喫緊の課題であると考えています。そのような学生たちが少しでも興味をもって学習を進めることができるよう、おもしろさの理由づけができている状態である認知的興味という観点から検討しています。勉強することってどのようにおもしろいのか、そのおもしろさはどのように形成されるのかを明らかにしたいと思っています。 リサーチマップURL:https://researchmap.jp/m_nakaoji |
| 自己紹介 | 学部から現在まで関西大学に所属して心理学を学んでいます。学部時代にキャリア心理学と出会い、自身もキャリアに悩んだ経験からキャリア心理学のゼミを専攻しました。自分の興味関心について、そのメカニズムを科学的に明らかにできる、またその成果を世の中に伝えることができることに魅力を感じ、大学院に進学しました。アカデミックな活動で日々思考を深めながら大学院生活を楽しんでいます。 |

| 名前 | 齋藤 遼太郎(SAITO Ryotaro) |
| 学年 | 博士課程 後期課程 3年 |
| 研究内容 | テーマ:水産学専攻を対象とした専門教育課程のおけるキャリア教育 漁業の衰退に伴い、日本の水産業全体で人手不足が深刻になりつつあります。そのような現状の水産業界に人材を輩出することが期待されているのが、四年制大学の水産系専攻(水産学科、海洋学科など)です。しかし、残念ながら水産系専攻の学生は、他の理系分野の学生よりも専攻と関連のある職業に就く学生が多くありません。では、なぜ水産系専攻の学生はあまり専門関連職に就かないのか?、専門教育課程でどのような教育を行えば学生がより水産業に興味を持ってくれるのか?ということに関心を持ち、現在の研究を始めました。水産系専攻に限らず専門教育課程におけるキャリア教育の知見はまだまだ不足していますので、他専攻のキャリア教育にも何かしらのヒントを提供できるものになればと考えています。 |
| 自己紹介 | 修士課程までは水産学を専攻しており、現在は社会人大学院生としてこの研究室に在籍しています。心理学とは無縁の学生生活を過ごしてきましたが、キャリアのことを研究したいと考え思い切って分野を転向しました。研究を通して漁業、ひいては地方の再興に少しでも貢献できるよう頑張ります。 |
博士前期課程
M2
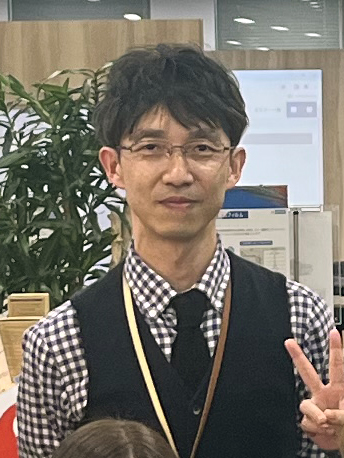
| 名前 | 小島 隆之(KOJIMA Takayuki) |
| 学年 | 博士課程 前期課程 2年(3年コース) |
| 研究内容 | テーマ:働くひとのプロティアン・キャリア志向(Protean Career Orientation)を促進する要因 ——キャリア・トランジションに焦点を当てて—— 自律的キャリアの代表的な概念の一つである「プロティアン・キャリア」について研究を行っています。人生100年時代,VUCAとも呼ばれる予測不能な現代,自己志向的なキャリア形成によって,変化に対応していくことが求められています。自分自身もプロティアン(変幻自在)なキャリアを歩んでいくことができればと思っています。 |
| 自己紹介 | TOPPAN株式会社で会社員として働きながら,社会人大学院生として入学しました。本業・兼業・育児・研究のマルチタスクは厳しいチャレンジになりますが,自分らしい悔いのない大学院生活を送りたいと思っています。 |

| 名前 | 張元享(CHANG Yuanhsiang) |
| 学年 | 博士課程 前期課程 2年 |
| 研究内容 | テーマ:仮想的有能感とオンライン脱抑制によって生じるToxic Behavior(仮) 私は,若者の仮想的有能感が形成される心理的要因およびその社会的影響について研究しています。特に,オンラインゲーム環境において仮想的有能感がToxic Behavior(味方や相手に対する暴言,挑発,執拗な妨害行為などのマナーに反する攻撃的行動)をどのように引き起こし,他者への影響や個人の行動にどのような変化をもたらすかなど心理的メカニズムを探ります。また,この研究を通じて,オンラインゲームにおける健全な交流環境の構築に寄与する心理学的な知見を提供することを目指します。 |
| 自己紹介 | 台湾からの留学生として,杉本先生の下で仮想的有能感について研究しています。元々オンラインゲームを趣味にしており,ゲーム内のチャットで見かける攻撃的な言動や軽視的な行動に疑問を抱き,調査を進める中で仮想的有能感という概念に出会いました。現代の若者文化において,仮想的有能感がどのような役割があるのでしょう。また,そのポジティブおよびネガティブな側面について深める理解を求めるため,大学院に通っていました。もし自分の研究が,人々の攻撃性や偏りのある評価を低減し,他人を傷つけたり傷つけられたりしない社会の実現に貢献できたら,嬉しいと思っています。 |
