
メンバー一覧
名前のボタンを押していただいてもご覧になれます
| 心理学 |

石津 智大
関西大学 文学部
心理学専修 教授
総合人文学科
わたしは神経美学と芸術認知科学の研究に取り組んでいます。
アート・感性と脳のはたらきとの関係を研究し、感性科学の実社会への応用を目指しています。
慶應大学で心理学博士号を取得した後、ウィーン大学心理学部研究員、ロンドン大学ユニバーシティ校生命科学部上席研究員を経て、現在は関西大学および広島大学脳・こころ・感性科学研究センターの客員教授も兼任しています。
わたしの研究は、人間の幅広いアート活動と認知プロセスの関係、感性的な体験と脳の機能との関係を、実験心理学と認知脳科学の手法を利用して解明することを目的としています。作品の知覚、表現技法、価値づけ、芸術的創造性など、アートにかかわる様々な側面と脳の機能との関連性を探ることで、人間の感性のメカニズムに迫ります。
さらに、基礎研究の成果を社会に還元することにも尽力しており、アートと美的体験を活用した公共空間・福祉施設のウェルビーイング促進など、感性科学の実践的な応用にも取り組んでいます。
KEWRTでは、神経美学と芸術認知科学の最前線の研究を共有させていただき、アートと科学の融合により人間の本質に迫るとともに、その知見を社会に役立てる新たな可能性を切り拓いていきたいと考えています。
| 総合人文学と映像文化 |
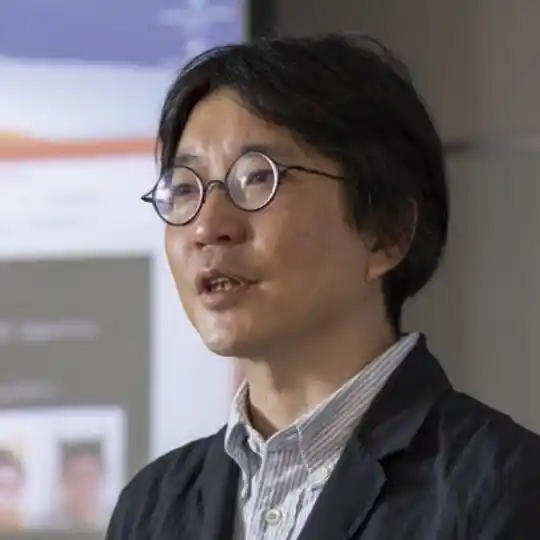
門林 岳史
関西大学 文学部
総合人文学科
映像文化専修 教授
メディアの哲学と映像理論が専門。もともと東京大学大学院での博士論文でカナダのメディア論者マーシャル・マクルーハンについて研究したのが研究者としての出発点ですが、現在は「ポストメディア」をキーワードにして現代のメディア状況についての理論的研究を進めています。
また、東日本大震災後、せんだいメディアテークや山形国際ドキュメンタリー映画祭などを主なフィールドとして震災後の映像メディアの実践についての調査にも取り組んできました。
教育面では、上記の自分自身の研究課題に加え、映像文化専修の学生の関心に対応して、VTuber、ゲーム実況、アイドルのファンダム研究など、多彩なテーマで卒論指導をしています。
その結果、最近TikTokでなにが流行っているかそれなりに詳しくなりました。
KEWRTでの役割
メディアと身体の関係について専門的な知見を提供します。
| 教育学、マインドフルネス |

小室 弘毅
関西大学 人間健康学部
人間健康学科
教授
研究テーマ・関心領域
東京大学大学院教育学研究科で教育人間学をベースに「教養=自己形成」についての研究をスタートしました。単に学力が向上するのではなく人が人として成長するとはどのようなことか?そこに携わる教育とはいかなるものか?そういったことを人文学的方法論から研究しています。
さらには野生のイルカとの交流を通して身体と呼吸の重要性に気づき、ヨーガへと導かれていきました。
以降身心未分の「からだ」をキーワードに、ヨーガの他、ソマティクスやボディワーク、ソマティック心理学やボディサイコセラピーを基盤に、身体と心の関係から人間形成の問題を探求しています。
近年はマインドフルネス、アート(荒川修作)研究へと対象領域を広げ、教育、人間形成における身心のあり方を研究しています。
KEWRTでの役割
ワークの開発、ワークショップファシリテーター等、実践面での展開を主に担当しています。また教育人間学的視点からの新しい価値観や観点の提供を行います。
| 心理学、身体心理学 |

菅村 玄二
関西大学 文学部
総合人文学科
心理学専修 教授
研究テーマ・関心領域
身体の動作と感覚の心理学が専門。
たとえば,両腕を曲げ,両肩を上に上げて,グッと力を入れるという身体動作をおこなうと,筋緊張という身体感覚(筋感覚)が生じます。
そのときの「緊張した感じ」は,体だけで感じられるのではなく,心でも感じられるのではないでしょうか。
逆に,電車でウトウトして,体の力が抜けた状態では,気持ちを緊張させることは至難の業です。
緊張は,身体が取りも直さず精神でもあることの好例です。
また身体をとおして,身の回りのモノや他者,あるいは自然環境を見たり聞いたり触れたり,あるいは匂ったり味わったりすることもできます。
こうした環境とのインターフェイスとしての身体に着目し,それが私たちの気分や感情,あるいは行動や思考スタイルにも影響するといったことを実験的に検証しています。
近年は,こうした知見を踏まえて,学習・労働環境での集中を促す座具の開発や,身体性を採り入れた道徳教育などにも関心をもっています。
KEWRTでの役割
心身のつながりや環境との調和を重視する身体心理学の知見や考え方に基づき,ビジョンや方向性についての視座を提供します。
製品開発の場合は,心理面(感情・思考・行動)での指標について助言することもあります。
| 現代哲学と現象学 |

三村 尚彦
関西大学 文学部
総合人文学科
哲学倫理学専修 教授
研究テーマ・関心領域
最近の研究テーマは、アメリカの心理学者・哲学者ユージン・ジェンドリンの体験過程理論。
これは、身体がさまざまな新しい意味や価値を作り出す創造性をもっていると主張するもので、それを手がかりに、リハビリテーション医療につながる哲学的身体論を構想しています。
また、現代美術家の荒川修作+マドリン・ギンズのアート作品や建築思想についての研究も行っています。
大学の授業では、ファッション哲学、VR(ヴァーチャルリアリティ)、AI(人工知能)などについても論じています。
KEWRTでの役割
チームの代表を務め、主にクライエントとの総合的な交渉・相談を担当しています。また哲学的思考を活かして新しい価値観や観点の提供を行います。
| 宗教/スピリチュアリティ心理学,教育・学校心理学 |

村上 祐介
関西大学 文学部
総合人文学科
心理学専修 准教授
研究テーマ・関心領域
「より良く生きるための教育とは?」というリサーチクエスチョンのもと,身体ー心ー環境の相互関連性に着目した研究を実施。
例えば,学習者の姿勢をサポートすることを通じて,授業中のエンゲージメントや生きがいの向上を目指す身体性教育を展開しています。
また,人生の意味をはじめとする「大きな問い」を扱う教育が,青年の学習観や心理的健康へ及ぼす影響にも関心があります。
近年では,ひとりの時間の欠如によって生じる苦痛を言い表す「アロンリネス」や,因果応報や輪廻転生に基づく「カルマ信仰」についての基礎研究にも着手しています。
KEWRTでの役割
ウェルビーイング論を中心に,プロダクトやサービスの潜在的な価値や意味を探るための視点を提供します。
また,心理学的研究手法のノウハウや,学校現場での介入研究の経験を活かした助言も行います。
| 人間健康学 |

村川 治彦
関西大学 人間健康学部
人間健康学科
教授
研究テーマ・関心領域
身体性をキーワードに、心と身体と環境の関係を実践的、体験的に探ることを研究テーマとしています。特に自らの「からだ」を一人称の立場から探求する東洋、西洋の身心変容技法の研究と応用に関心をもっています。出自は宗教学ですが、Somaticsと東西心理学を米国で学び、気功をテーマに博士論文を書きました。(つまり、怪しい)
今取り組んでいるのは、多様性と循環を軸に「街のようにキャンパスで出合い、キャンパスのように街で学ぶ」場作り、米国で開発された医療、看護、福祉など対人援助領域でバーンアウトを防止するためのGRACEプログラムの紹介などです。
KEWRTでの役割
対人援助職全般に、体験的アプローチでの教育研修プログラムの開発、提供などを行います。