
研究活動
Research Activities
– 2009
カイロ大学からの交換研究員
平成21年 (2009年) 12月
関西大学とカイロ大学の学術協定によって、カイロ大学考古学部から2名の研究者が関西大学に派遣され、共同研究がおこなわれました。エル・サイエッド・エル・バンナ教授(保存修復学科)、アフメド・シュエイブ教授(保存修復学科)のお二人であり、それぞれ1ヶ月、2ヶ月滞在されました。昨年のアフメド・ガラル教授(エジプト学科)とサラーハ・エル・コリ教授(エジプト学科)に続くものです。
文化財保存修復研究拠点では、この機会に両先生と研究上の意見交換をはじめいくつかの研究会を行いました。このような活動には、本拠点の研究員ばかりではなく、院生、学生も参加し、日本には蓄積がないために十分にはできないエジプトなどアラブの文化財の保存についての研究を行いました。
エル・サイエッド・エル・バンナ教授は、青銅器の保存とイエメンの歴史都市の保全、アフメド・シュエイブ教授は、壁画の保全が専門分野になります。また、両先生は、下記にあるシンポジウムにも参加されています。
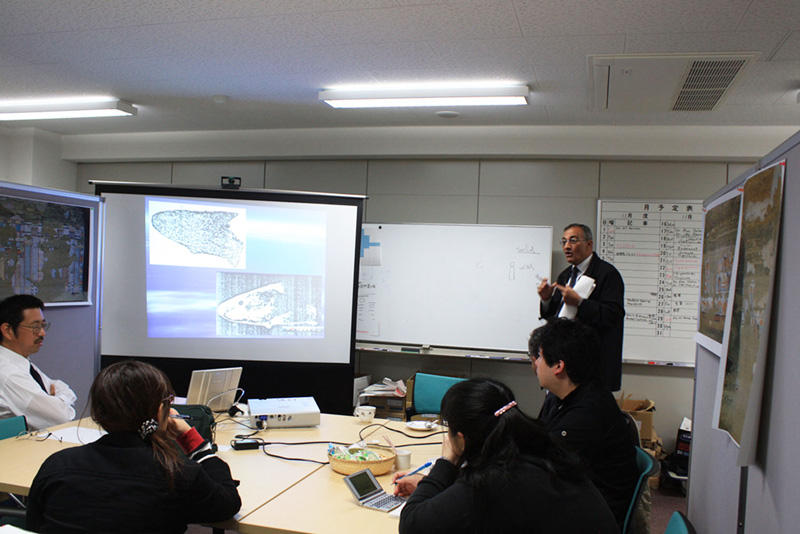
第1回国際シンポジウム開催
平成21年 (2009年) 11月21~22日
第1回国際シンポジウムを関西大学にて開催いたしました。このシンポジウムは、拠点研究員の研究成果の発表をおこなったものです。また、カイロ大学から、エジプト学者のアラ・シャヒン教授を招聘するとともに、関西大学とカイロ大学の学術協定によって本学に来られていた、文化財修復研究者のエル・サイエッド・エル・バンナ教授にも発表をお願いしました。
発表内容は、研究拠点の研究課題に沿って多様なものになっていました。古代エジプトの壁画に関しては、「保存修復班」のエジプト人研究者からの壁画の劣化の具体的なプロセスを踏まえた発表は国際的にも貴重なものでした。また「文化・都市班」の発表は、従来のエジプトの調査隊が行ったことのないものであり、「技術開発班」の発表も、エジプトとの共同研究ならではの成果を持っておりました。
「地盤班」の堅実な成果蓄積に加え、「保存修復班」の日本人研究者からは、この研究の国際的な位置づけが行われました。このシンポジウムは、研究内容が文理にわたって多様であるばかりではなく、国際性と学際性にも特色のあるものになっていました。

日本・エジプト合同マスタバ・イドゥート調査ミッション
平成21年 (2009年) 7月~9月
日本・エジプト合同マスタバ・イドゥート調査ミッションの第7次調査として、サッカラのイドゥート遺跡の壁画修復のための調査を行いました。
壁画の劣化の大きな原因となっている岩盤の劣化状況を調査しました。このような地学上の問題は、このサッカラ地域のみならず、ギザ地域にも当てはまるものです。地下埋葬室内に設置した変位計などのデータを回収するとともに、地盤構造の解析データの収集を行いました。さらに、サッカラ地域の岩質の調査も行いました。
前の調査に引き続き、埋葬室内の環境データ(相対湿度、気温)を回収するとともに、壁画修復の方法と材料を検討しました。現在、壁画のはぎ取りによる修復技術の改良につとめていますが、地下埋葬室の壁画の劣化の状態は一様ではないために、修復方法も対応したものを開発しています。
同時に、古代エジプトの文化財のあり方の研究を続けています。研究を行っている壁画は、本来どのような姿をしていたのか、修復の際本来の姿はどのように扱われるべきかなどを、他の遺跡とも比較しながら検討しました。また、遺跡と地域コミュニティーの関係を探るべく、サッカラ村のフィールド調査も行いました。
古代技術を解明し、修復に役立てるために、携帯型蛍光エックス線分析装置などを用いて、古代壁画の顔料など各種の分析も行っています。
※なおこの調査に並行して、住友財団の助成によって、壁画の修復作業も行われました。


日本・エジプト合同マスタバ・イドゥート調査ミッション
平成21年 (2009年) 2月~3月
日本・エジプト合同マスタバ・イドゥート調査ミッションの第6次調査(後半)として、サッカラのイドゥート遺跡の壁画修復のための調査を行いました。
伊藤淳志氏(地盤工学)、西形達明氏(地盤工学)の両氏は、地下埋葬室内に設置した変位計などのデータを回収するとともに、地盤構造の解析データの収集を行いました。西浦忠輝氏(保存科学)は埋葬室内の環境の維持システムを解明するデータを回収し、調査を行いました。高鳥浩介氏(微生物化学)はエジプトの文化財におけるカビの実態調査を行い、岡絵理子氏(都市計画学)はエジプトの文化遺産都市を訪問し、その生活実態の調査を行いました。吹田浩氏(エジプト学)は、文化財の劣化の実態の解明に努めつつ、イドゥートの壁画の修復方法の開発を進めました。また、エジプト側の共同研究者、アフメド・シュエイブ氏(保存科学)、アーデル・アカリシュ氏(地球科学)は、埋葬室の現状に応じた修復方法の新しい方法を検討しました。現地では、これらの研究者で共同で検討を行い、イドゥートの壁画の現状の把握に努め、新しい技術の可能性を模索しました。
※なおこの調査に並行して、住友財団の助成によって、壁画の修復作業も行われました。

エジプト人研究者の来日と研究
平成21年(2009年)1月
共同研究者であるアフメド・シュエイブ氏(カイロ大学)とアーデル・アカリシュ氏(国立研究センター)が、2009年1月に来日し、関西大学にて各種の調査を行いました。関西大学の各種ある分析機器、文化財保存修復拠点が所有する機器を踏まえて調査計画を立てるとともに、古代エジプトの壁画技術の研究を共同で行いました。

エジプト調査
平成20年(2008年)12月
土戸哲明(微生物学)、川崎英也(化学分析)、中村吉伸(高分子化学)、森貴史(博物学)、中澤務(古典学)、吹田浩(エジプト学)の各氏からなる日本側のグループがエジプトを訪問し、エジプト側の研究者であるアフメド・シュエイブ氏(文化財科学)、アーデル・アカリシュ氏(地球科学)とともに、調査と打ち合わせを行いました。
主な目的は、エジプトの遺跡の現状を各分野から確認するとともに、研究機関の研究者と意見交換を行い、今後の調査の手順を検討するものでした。また、微生物などのサンプルを確保することも大きな目的でした。
サッカラ遺跡群では、ジョゼル王の階段ピラミッド、メレルカのマスタバ、「二人兄弟」や「肉切り職人」の岩窟墓などを訪問しました。サッカラの遺跡群は、エジプトでも最大の遺跡群であり、ピラミッド、マスタバ、岩窟墓など多様な遺跡が三千年の長きにわたって残されています。このような遺跡は、それぞれの遺跡を単体で扱うのではなく、遺跡群としてとらえ、遺跡としての在り方を古典学や博物学から検討し、エジプト学の立場とともに遺跡の活用を考える資料を収集しました。
サッカラでは、特にジョゼル王のピラミッドの南に隣接したイドゥートのマスタバ(紀元前2360年ごろ)を研究対象としています。このマスタバの地下には美しい壁画が残っていますが、地盤がもろいため多くが剥落し、永久に失われる危険な状態にありました。そこで、2003年度から調査を開始し、2005年度から修復事業を行っています。今回、高分子化学の立場から新しい修復資材の開発を現地の観察を踏まえて行うことになっています。また、微生物の問題があるかを調査しました。
現地の研究者との意見交換を行うためにカイロ大学考古学部と国立研究センター(The National Research Centre)を訪問しました。カイロ大学考古学部では、学部長アラ・シャヒーン博士をはじめ研究者と考古遺跡についての意見交換を行いました。関西大学は、2006年にカイロ大学と学術交流協定を締結し、考古学部から教員を受け入れて、エジプト学・文化財科学の研究を行っています。
国立研究センターは、エジプトで最大の総合的な研究機関であり、三千名の研究者がいると言われています。地球科学部門を中心に化学分析部門などを訪問し、研究者と意見の交換を行いました。化学分析設備を実見したことは、相互の理解を深めて、研究計画をたてることになりました。
また、多様なエジプトの遺跡の実態を理解するためにデルタの遺跡、アレクサンドリアのカイト・ベイ要塞、イスラム地区などを訪問しています。デルタでは、上エジプトとは異なった文化財の性質と文化財に対する脅威があります。アレクサンドリアも、地中海に面していることから、同じように特有の問題をかかえています。イスラム地区は、現在、観光のための整備が進められており、遺跡の活用の観点から調査を行いました。
このエジプトでの調査によって、日本人の専門家とエジプト人の専門家のあいだに研究上の相互補完的な協力関係を強化することができました。今後、研究拠点では研究をさらに発展させていくつもりです。




